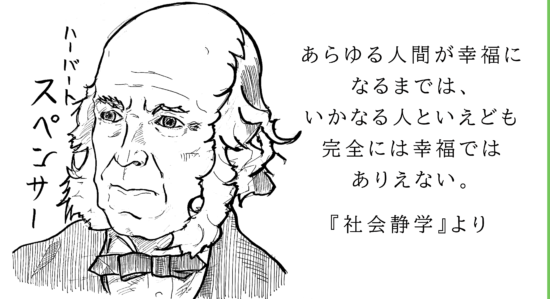目次
【1章 母・メアリー・スチュアート】 【2章 幼児体験】 【3章 魔女裁判】【1章 母・メアリー・スチュアート】
16世紀前半のイギリス国王ヘンリー8世は、6回の結婚をしています。
1回目は18歳のとき、キャサリン・オブ・アラゴンと。
彼女とは14年間の結婚生活を送り、後にヘンリー8世の2代後に女王となるメアリー1世を生んでいます。
2回目は42歳のとき、アン・ブーリエンと。
3年間の結婚生活を送り、後に3代後に女王となるエリザベス1世を生んでいます。
3回目は45歳のとき、ジェーン・シーモアと。
1年間の結婚生活を送り、後に次の代の国王エドワード6世を生んでいます。
この奥さんジェーン・シーモアは、兄がエドワード・シーモアで弟がトマス・シーモアで、次の代の国王エドワード6世の政治のときに兄弟が大きな影響力を及ぼします。
4回目は49歳のとき、アン・クレーブスと。
すぐに結婚生活は終わりを告げます。
5回目は同じく49歳のとき、キャサリン・ハワードと。
2年間の結婚生活を送ります。
6回目は52歳のとき、キャサリン・パーと。
3年間、ヘンリー8世が亡くなるまで結婚生活を送ります。
実は3回目の奥さんの弟トマス・シーモアの恋人だったのですが、ヘンリー8世が見初めて結婚することになりました。彼女は教養高くヘンリー8世の話し相手になり、またエドワード6世はヘンリー8世のもとに最後に生まれた男児であったため王位継承権はあったのですが、かつての奥さんの娘たちはメアリー1世とエリザベス1世の王位継承権は微妙なものであったのですが彼女が娘たちも王位継承権保持者として認めさせました。
そして1547年ヘンリー8世はなくなります。
ヘンリー8世は最後の奥さんキャサリン・パーにも十分な処遇を約束してなくなったのですが、キャサリン・パーはかつての奥さんの息子エドワード6世が王位に就くため、遠慮してか王室を出ていきます。そしてかつての恋人トマス・シーモアと再婚しました。
エドワード6世の母親の兄であるエドワード・シーモアはまだ幼い国王に変わって政治を執ります。そして、当時は別の統治であったスコットランドの支配のために、スコットランドの時期女王メアリー・スチュアートと結婚することを目論みました(もともとヘンリー8世のときにエドワード6世とメアリー・スチュアートは婚約をしていました)。メアリー・スチュアートはヘンリー8世の兄弟の娘に当たりエドワード6世と同じく王位継承権の強い立場でもあったので、関係を強めようという目論見もあったのでしょう。
しかし、メアリー・スチュアートの母はもともとフランス国王の娘でもあり、フランスとイギリスは当時敵対関係でもあったためスコットランドとフランスの連携を優先し、メアリー・スチュアートはフランス宮廷に避難させ、フランス王との婚約をすることでエドワード6世との結婚を破棄しました。
フランス宮廷で生活しているときに後にスペイン王フェリペ2世の3度目の奥さんとなるイザベルも同じく幼少期を過ごしてました。そして後にフランス国王フランソワ2世と結婚します。
さて、エドワード6世は1553年わずか6年くらいで亡くなってしまいます。
その次の王位継承者としては、ヘンリー8世のかつての娘(メアリー1世やエリザベス1世)は離婚したときの娘であった関係から立場が危うくなり、メアリー・スチュアートと同様ヘンリー8世の兄弟の娘ジェーン・グレイ(「怖い絵」などで有名)が選ばれます(メアリー・スチュアートはフランス王と結婚してた関係からおそらく選ばれなかったのもあります)が、政治的紛争が起こり、すぐにメアリー1世が女王として選ばれることになります。
メアリー1世は即位し、すぐに次期スペイン王フェリペ2世と結婚します。そのため、プロテスタントやイギリス国教会(ヘンリー8世がカトリックで認められていない離婚を達成するために形式的にはカトリック的だが教皇の庇護下にない宗教)も蔓延っていたイングランドをカトリックに統一すべく多くの流血を伴った政治を行います(「ブラッディ・マリー」と呼ばれる)。
ただ、メアリー1世は不妊である疑いが強くなり、次の王位継承者としてエリザベス1世を特に夫のフェリペ2世は考え始めます。その頃、スペインはフランスと争っていて、メアリー・スチュアートが次期女王になるより、まだエリザベス1世の方が良いと判断したためでした。
そして1558年、メアリー1世は5年ほどの治世でなくなります。
そこでエリザベス1世が女王に選ばれます。
ただし、カトリックの視点からみるとエリザベス1世より、メアリー・スチュアートの方がイングランドの王位継承者としての資格が強く、メアリー・スチュアートはエリザベス1世が即位しても王位継承者を名乗ります。
そしてエリザベス1世が即位して2年後の1560年、メアリー・スチュアートの旦那さんであるフランス国王フランソワ2世が若くして亡くなってしまいます。そのため、メアリー・スチュアートはスコットランドに帰国して、スコットランド女王は生まれたときから継いでいましたが、本国に戻り女王として政治を執り始めるのです。
こうして後のイギリス国王ジェームズ1世が生まれる状況が整います。
【2章 幼児体験】
ジェームズ1世は、スコットランドの女王メアリー・スチュアートから1566年に生まれました。
1560年に、メアリー・スチュアートがフランスからスコットランドに戻ってきたときは、プロテスタントに宗教改革が進んでいて、カトリックとプロテスタントが緊張した状態で併存していました。
そのため、メアリー・スチュアートはカトリックでしたが女王として政治を執る際には、プロテスタントに寛容な政治をしました。
そんな不安定な中にメアリー・スチュアートはおそらく自分の女王としての立場を強めるために再婚を考えます。
案としては、スペイン王フェリペ2世の息子ドン・カルロスなどもでましたが、結局同じくヘンリー7世を曾祖父にもつダンリー卿ヘンリーと1565年に結婚します。
イングランドのエリザベス女王も曾祖父に持つため、今回の結婚はエリザベス女王に対してもメアリー・スチュアートのイングランドでの影響力を強める結果になる有意義なものでした。周りの者たちはイングランドの勢力をスコットランドに引き込むことになるためか、あるいはカトリックの力を強めるためか非常に反対しますが、メアリー・スチュアートは強引に結婚を進めました。
そんな中、メアリー・スチュアートの秘書リッチオもダンリー卿ヘンリーの味方になり祝福します。しかし、そんな祝福してくれて秘書リッチオにダンリー卿ヘンリーは嫉妬心を抱き、メアリー・スチュアートの目の前で殺害させるという事件が起こります。原因は、ダンリー卿ヘンリーはあまりにもわがままでメアリー・スチュアートの味方になるどころか弊害になり始めたため、奥さんであるメアリー・スチュアートに見放されたため、寵愛を受けていた秘書リッチオに嫉妬心を抱いた事にあります。そして、その現場にメアリー・スチュアートのお腹の中に胎児としてジェームズ1世はいました。
そんなこともあったのでメアリー・スチュアートとダンリー卿ヘンリーとの夫婦関係は完全に終わってしまったのですが、女王である立場上、また女王としての立場を強めるためにはダンリー卿ヘンリーと仲直りしなくてはならないため、メアリー・スチュアートはダンリー卿ヘンリーの基に行き一時仲直りしますが、ダンリー卿ヘンリーが殺害されるという事件が起こりました。
実体はリッチオ殺害による恨みによって貴族から暗殺されたとも、ダンリー卿ヘンリーが妻のメアリー・スチュアートに対する嫉妬心が再燃して暗殺しようとした手違いから自分が殺害してしまったとか言われますが、当時はメアリー・スチュアートのもとで活躍していた第四代ボスウェル伯に嫌疑が及びます。
こうして女王メアリー・スチュアートは、夫を失い、力になっていたボスウェル伯の立場が危うくなり力を失い、スコットランドを抑える力がなくなり、女王を退位しまだ1歳であるジェームズに国王の座を継ぐことになりました。
そして、元女王の勢力と国王ジェームズの勢力による「メアリー国内戦争」(Marian civil war)が1568年から(1573年まで)始まります。
そんな事もあり、その時点でまだ幼児であったジェームズと母メアリはそれ以来顔を合わせることがなかったといいます(メアリーはその後1568年からイングランドに亡命する事になることもあります)。
国王ジェームズは1歳であったため、摂政としてモーレイが政治を執りますが1570年に暗殺されてしまいまいます。その後、ジョージ・ブキャナン(George Buchanan)という「16世紀のスコットンランドで排出された最も高い知性」とも称された人が政治やジェームズの家庭教師なども務めます。特にブキャナンは、ジェームズのもとにはカトリックに基づく神によって与えられた国王の考え方を勧めるものが多かった中、プロテスタントに基づく国王の立場を限定的に考える思想を教えたとも言われています。
このように幼少期は、生まれる前から母親の女王としても家庭の母としての立場も安定せず、また生まれてからも母親とはすぐに別れ、更に国王としての立場も安定しない混乱した内戦の中、ジェームズ1世は育ったといえます。
【3章 魔女裁判】
ジェームズ1世が20歳の始まりの頃、プロテスタントの貴族に捕囚され、徹底的にフランスとカトリックの影響を排斥される事件が起こります(1582 Raid of Ruthven)。
ただ、カトリックとフランスの影響はジェームズ自身も払拭したものの、プロテスタントの自身への影響を否定し、かつてジェームズにプロテスタンティズムに基づく制限の中での国王を教えた家庭教師ブキャナンの事を否定します(1583)。
そして、ついに1587年母親のメアリ・スチュアートが処刑されるとフランスやカトリック・プロテスタントによらない自分自身の正統性を確立することに努力の方向が向き(最もカトリック・プロテスタントは完全に否定ではなく許容はした)翌年にはカトリックの大御所スペインと戦ったエリザベス女王のイギリスに急速に接近します。
そこで地に足を付けるため、1589年自分自身の力を増すための結婚を考え始め、プロテスタントの王・フレデリック2世の娘・アンと結婚する事になります。
フレドリック2世といいますと、プラハのルドルフ2世のもとでケプラーと共に研究したティコ・ブラーエに、研究のために大きな援助を与えた王としても記憶されます(デンマークの後にティコはルドルフ2世のもとに行った)。実際、ジェームズ1世がデンマークに行った際、ティコ・ブラーエとジェームズ1世は宮廷で会っています。ただし、フレデリック2世は当時はもう亡くなっており息子のクリスチャン4世の治世にはなっていました。
その結婚のためにジェームズ1世がデンマークに行った帰り、なんと船が嵐に巻き込まれ1隻は沈没してしまいました。そこで、その嵐が起こったのはデンマークとスコットランドで魔女が魔術を使ったため事件が起きたとして、裁判が行われたのです。
デンマークでは以前から魔女裁判が行われており、このデンマークでの結婚を機に、ジェームズ1世がデンマークに習って、スコットランドにおいても魔女裁判を行いました(1590-1 North Berwick with trials)。
この魔女裁判において、「国王はサタンが相手にする世界最大の強敵である」「かの人は神の子である」など国王が神の使いであることを意識させる効果があったといわれています(『魔女幻想』度会好一著参照)。
ジェームズ1世自身も魔女裁判の正統性を高めるため『悪魔学』という悪魔や魔女に関する体系的な著書を描き、その著作の冒頭にこの裁判を記載した程でした。
この著作が書かれたのは1597年ですが、イングランドで後に発刊されたのは1605年頃で、この『悪魔学』の裁判のことの影響も受けて、魔術師が登場するシェイクスピアの『マクベス』が作られたとも言われています。
ただ、ジェームズ1世は『悪魔学Daemonologie』という著書だけだと君主の人格を疑われそうですが、翌年1598年に書いた『正しい方における自由な君主(The true law of free monarchies)』では王の正統性を論理的でありながら読みやすく描き、1599年の『Basilikon Doron』という著作では息子に向けた手紙において帝王学を語るという切り口で、君主論を説いていますが、そこでも深い知識の勉強が必要な事や分かりやすく明快に話すことが大切など、優れた人格と理性を備えた国王像が感じさせられます。